脱欲界──欲界からの解脱──
先日まとめた仏教の六欲天についての考察のその先の話として、欲界そのものからの離脱(解脱)について考えてみる。
| 身 | 口 | 意 | |
|---|---|---|---|
| 善業 | 地居天 (四大王天+三十三天) | マノーパドーシカ (夜摩天+兜率天) | キッダーパドーシカ (楽変化天+他化自在天) |
| 悪業 | 餓鬼 | 畜生 | 地獄 |
欲界に囚われた心(精神)の持ち主(要するに凡俗)は、善にせよ悪にせよ、カルマ(欲)に基いて行為(業)を行うので、必ず、カルマを積み続ける。彼ら在家の世俗人は基本的に完全に欲界に囚われた思考回路の持ち主なので、価値観の全てが、善悪の区別にある。大乗(非仏)教を始めとして、本物の仏教以外の外道異教は、基本的にその善悪の区別において、各価値観モデルを競い合っている。これが、スッタニパータにおいて、「俗世間における論争の生じる」とされる構図であり、「聖者では鎮まる」とされるところのものである。
仏教の聖者とする人々は、善にせよ悪にせよ、カルマ(業報)を伴なう行為(因業)にほとほと嫌気が指した思考回路を持つ人々であり、まずはその段階で大きく、世俗人(外道異教の聖職者を含む)と思考回路的に根底から違っている。「何が善か」という、善の具体的内容を思い描くことなどから離れているのである。なので、仏教において、〝善〟という用語を、情報伝達のために世俗諦として語る場合には、メタな形で用いており、不悪(不貪・不瞋・不痴)という否定表現で言われたり、善悪を含めたカルマの世界である欲界から丸々離れる(解脱する)ことを指して使われる。
今回の僕の仏教仮説では、このように、欲界から離れた(解脱した)聖者の世界・境地として、色界・無色界の梵天界を捉え、従来語られ・思われているような「座禅瞑想して禅定状態に入ることで行くのが、色界・無色界の梵天界である」という捉え方とは、別のイメージで捉えようとするものである。
客体論と主体論
今回の考察では、欲界(世俗の世界)をひとまとめにして捉え、脱欲界(である色界・無色界の梵天界)と対比することで、出家者の世界である梵天界をはっきりと浮き彫りにしようと思う。
まず、欲界に心が囚われている世俗人は、価値判断の思考回路的に、当たり前のように客体論で客観的〝真実〟(正解)があると思っており、その正解を探そうとする。この思考様式が適切であるのは、物質世界を対象とした自然科学の分野に限定されるのだが、知性の低い凡俗は、この思考様式をノーガードで万事に適用しようとするのである。「一事が万事」「馬鹿の一つ憶え」などとは、古人もよく言ったものである。
しかし、仏教の正解は、主体論(第一者視点・主観論)として説かれているとして読み解くことにある。この段階で、完全に、欲界の人々の価値観・思考回路とは相容れない。例えば、仏教は「この世界は空である」などとは決して言っていない。そんなことを言っているのは非仏教(の大乗教)である。(本物の)仏教は「この世界を空と観じなさい」と、瞑想論の文脈で、観法(観察方法、すなわちヴィパッサナー論)として説いている。あくまでもこの世界を観ている観察者本人の主体の在り方、主体論として一貫して説かれているのが仏法である。客体論(自然科学のような客観的普遍性のある一般論)として説かれていない。だから、般若心経は「色即是空、空即是色(この物質世界というものは空である)」という客体論を説いていることからして、完全に非仏教である(cf. また他方、スマナサーラ長老は、論理学的な側面から、必要条件と十分条件を混同しているという初歩的な般若心経の捏造者の知性的欠陥を指摘している。欲界に囚われた精神による作品というのは、所詮はこの程度ということである)。
輪廻転生と無我論
日本の仏教研究者でも、輪廻転生と無我論の擦り合わせに成功している人はあまり見られない。もちろん、テーラワーダからすれば「輪廻転生の主体などなく、業相続によって輪廻転生する」で、簡単に片付く問題だが、日本の仏教研究者は「主体なき輪廻転生」を当人の確信を以って世間の人々に示せるわけでもないのである。他人事(第三者視点)として「テーラワーダではこう解されている」という程度である。(注:「輪廻転生の主体」という場合「主体」は、前述の主体論・客体論という意味の「主体(第一者)」ではなく、あくまでも客体論(第三者視点)の下での「誰が」を指して言っている用法であるのがわかる)
この無我論というのも、欲界からの解脱ということと密接に関係しているため、欲界の範囲内での議論で、他の人々に示せるような語り方はできなくても不思議ではない。我執(「私のもの」「私である」「私の魂である」)という思考は、欲界に起因するものだからだ。なので、欲界の人々(世俗人)は、必ず、輪廻転生について考える場合、その輪廻の主体となるべき我執をベースとする。なので、輪廻転生を肯定しようとする場合、我(≒魂)の肯定はセットとなり、輪廻転生を否定しようとする場合、我(≒魂)の否定もセットとなる。日本の仏教研究者たちも、世俗人である限り、この思考にあるから、彼ら自身も自身の考えとしては、上手く説明できない。あくまでも「仏教ではこう言われているよ」と第三者事として語れるのみ、である。
なので、宗教・スピリチュアル的な超常主義者たちは、不滅の霊魂を頑なに主張した上で、輪廻転生を肯定しようとする。一方、霊魂などという迷信・盲信の産物を受け入れられない物質的現実主義者たちは輪廻転生は当然否定するし、たとえ仏教に携わる者であっても、輪廻転生を黙殺して避けようとする。
これが欲界というものであり、世俗人の限界なのである。
両者(超常主義者・現実主義者)いずれにせよ、欲界に完全に心が囚われているので、まず、現に今、物質的現実世界において、こうして肉体を持って生きている、生命としての我・自己の存在については、無批判に肯定している。問題は、そのような我が肉体的生命が終わった後も存続するかどうか、という極めてしょうもないことで論争が生じているのである。この我というのは、欲界的認識によって生じている我である。仏教が否定するのは、そもそものこの欲界的思考回路の認識によって生じている我が、無い、「無我だ」ということなのだ。
まず、超常主義者たちは、スピリチュアリスト(霊性主義者)などと、物質主義の対極を標榜しながら、その思考は、今現に、こうして肉体的生命を持って生きている、その物質世界の中で生じている個我のイメージが出発点にあることがわかる。それが、死後も存続して欲しいものだから、物質ではなく、別のオカルト的な次元の物質(霊魂)によって、維持される、と妄想設定を構築するわけである。
主体論=一人称視点、客体論=三人称視点
仏教で説かれている心(精神)というのは、超常主義者のような物質モドキのものではない。一人称視点のことを指している。超常主義者が霊魂のことを頑なに主張するのは、客体論(三人称視点で一般性を以って捉えられるもの)として輪廻の主体が存在すると思いたがっているのである。そうではなく、仏教で説かれている業による輪廻というのは、一人称視点としての主体論(主観論)であり、主観を離れて客観世界に自立して存在するものではない。
たとえば、世の霊能者は(僕が見る限り)ことごとく、心霊的なものが、心霊スポットなり、事故物件なり、墓なり、仏壇なり、どこか特定の場所に、存在しているかのように語っているが、僕はそれは間違っている、表現としては不正確である、と考える。心霊的なものは、あくまでも、人々の主観世界、要するに心の中に存在し、捉えられるのであって、それとは無関係に自立して、どこそこの客観的物質空間に存在しているのではない、はずである。
「メカニズムとしては、ただ、物理的に特定の場所に行くことで、各人が、主観世界の特定の場所に移動することをも意味している」と言った方が正確で語弊のない言い方である。
要するに、三人称視点でさも当然のように物事を考えること自体、欲界に囚われた精神のなせるわざ、ずぶずぶの凡俗の思考特性だということになる。超能力だとか、超常現象だとか、UFO・UMA だとか、果てには、マイトレーヤだとかのムー愛読者の好きそうな界隈、世直しだとか、大乗教なども、その延長にあるのがわかる。何しろ、世直し、救世主などという発想も、主観的世界、主体論ではなくて、この物質的現実世界をどうこうしようという発想以外の、何物でもないわけである。あくまでも客体論の範囲内にある思考の産物だということがわかる。

Unsplash の K. P. D. Madhuka が撮影した写真
梵天界=出家者の世界
以上までに述べてきたような欲界の愚かさにほとほと嫌気が指した極めて少数の高貴な精神の持ち主が、欲界を離れると、達することになるのが、色界に始まる梵天界なのではないか、というのが僕の仏教仮説である。つまり、このように欲界を離れる・出ることを出家と言い、欲界の別名は「家」である(cf.「家の作り手」)。だから、出家とは、比丘サンガで儀式を経て「お坊さんの身分になる」ことを直接指して言うのではない。家=欲界を出ること、だと考える。
そうすると、仏教的に言う、出家とは、極めて高度な、得難い境地であろうと思う。パーリ経典(『沙門果経』等)では、そのような出家を念頭に置いているから、禅定(初禅)について語られる時、「欲界を離れたことによる喜び」という表現になっているのだと思う。大乗教思考に汚染された、特に日本の仏教界隈のイメージだと、座禅して、瞑想して、恣意的に、禅定状態という、一種の精神集中的な変性意識状態を作り出すような印象で捉えられているが、違うのではないか。出家して(欲界を出て)いない、凡俗が、恣意的にサマーディーになっても、初禅にすら行けない、行く資格すらない、のではないか。一方、出家であれば、ほとんど自動的に、元から初禅に達しているも同然である。
つまり、パーリ経典で語られる初禅から第 4 禅に至る描写は、出家によって初禅に達している比丘が、単に、瞑想して、より雑念を除去して、心の精錬度を上げている様子を語っているのである。
基本的に仏教は出家者を対象とした教え
基本的に仏教は出家者に向けて説かれた教えだと思う。そのため、出家していて心が欲界から解脱した状態の人でなければ、適切に理解できない。「勝義諦」というような言い方もされるが、同じ言葉を情報・知識として聞いたとしても、凡俗と出家者では受け止め方、理解のされ方が違ってくるのである。これが主体論ということである。客体論であったならば、経典にあれこれ精通した仏教学者・研究者と、本物の出家比丘との間に、違いはないと考える。が、決してそうではない、のである。仏教とは、主体論として説かれたものなのだから。
因と縁
さらに僕の仏教仮説を述べるが、「縁」というのは客体論的な物事と密接な(世俗諦的な)概念であり、一方、「因」というのは、主体論的な物事と密接な(勝義諦的な)概念だと思う。「因縁」としてまとめて何となくわかったような感じて受け止めているだけでは、考察が甘いと思う。註釈的説明では、「因」が植物の種子そのものであるのに対して、「縁」は土や水や日光など環境的要因、という形で、植物の発生に例えて「業」を説明するのに使われていたと思う。
例えば、僕が気付いたのは、「因果応報」とは言うが、「縁果応報」などとは決して言わないということである。パーリ語でもそういう対応になっているのか、たまたま訳語がそうなっているだけなのか知らないが。また、独覚仏陀は、「独覚」というのは意訳だが、パーリ語に忠実な訳だと「縁覚」である。「因覚」とは言わないのがミソである。つまり、世間では「因縁」というセットで受け止められている場合が多いが、因と縁とでは実は全然違うのである。
例えば、大乗系の日本の仏教研究者は、ヤケに、「十二縁起」を重視する傾向があるが、彼らが、客体論的な思考で、「釈尊は菩提樹の下で何を悟ったのか?」という答え(悟りの客体)として、「十二縁起説」なのだ、と考えるからである。
だが、実際のところ、パーリ仏典では、四聖諦の方が圧倒的に繰り返し説かれている。つまりこれが主体論としての仏教の説かれ方なのである。これは苦の原因、要するに「因」について述べられたことだ。「縁」ではない。
つまり仏説とは、欲界を離れた出家者のみが適切に理解することのできる、主に「因」についての教えなのである。別の表現で言うと、勝義諦という言い方をされたりもする。一方で、「縁」というのは世俗諦的なものであり、限りなく客体論寄りの概念である。縁覚(独覚)仏陀が、他者に説いて他者を覚り(阿羅漢果)に導く資質に欠くのは、主に彼自身の縁を高めて阿羅漢果に達したからである。阿羅漢果に達した因は彼にとって無自覚的なものであり、一般化・言語化して他者に教えられるものではなかった、ということではないか。(ちなみにこの「教えの言語化」の点で、中国仏教の禅宗というのは、正覚仏による真正の仏教というよりは、「独覚仏道」と呼んだ方が適確かもしれない)
| 欲界 | 色界・無色界 (脱欲界である梵天界) |
|---|---|
| 在家 | 出家 |
| 客体論(三人称視点) | 主体論(一人称視点) |
| 我 | 無我・梵・業 |
| (外)縁 | (内)因 |
| 外道 | 中道 |
| 縁覚 | 正覚 |
| 世俗諦 | 勝義諦 |
欲界における因と縁と業
これも僕の仮説的な業に関するモデル。業は自由意志によって行われるもので、次生における縁を集める因となる。善業(善因)は良縁を、悪業(悪因)は悪縁を呼ぶ。因だけあっても縁に恵まれなければ、今生における果を結ぶことはない。前世の悪業による何らかの不自由な境涯は、生まれ持った悪縁として働く。前世の善業による何らかの恵まれた境涯は、生まれ持った良縁として働く。生まれ持った良縁に恵まれ(悪縁に縁遠け)れば、悪業を行ってもその生において悪果になることはないが、次生では縁がリセットされるので、今生における身・口・意の悪業を因とする縁によってストレートに構成される肉体を持って新たに生まれることになる。反対の場合(生まれ持った悪縁(良縁に縁遠い)、善業に努めても今生では報われないが、次生に生まれ持つ良縁として影響する)も然り。
つまり、善人は、善業(心の善良さ)が次生の身体に反映される。逆(悪人の場合)もしかり。ただし、欲界的な思考だと、結果主義的になって縁の側面を因の側面と区別して思考しないので、今現に、美しい者・美しくあることを好ましく思い、その内面での身・口・意の業を見ようとしない。今現に美しければ、その者の努力(善因となる業)は少なくとも、今生において良い結果を生むが、そのため善業に努める量は少なくなる傾向がある。それは次生に影響する。反対に、今現に、逆境にあるものは、努力(善因となる業)が今生において実りにくいが、その分、善果を楽しむ余地も少なく、ひたすら善業に努める傾向がある。それは次生に影響する。悪い場合だと、今現に、恵まれない状況だからと、どうせ大した結果を享受できないからと、いじけて善業を怠り、場合によっては悪業に走る場合は、次生ではますます悪いコンディションに恵まれた状態からスタートする羽目になる(cf.「業からは逃げられません 病気の人こそ慈しみを育てる必要があります」 )。仏教的な思考ができる、縁と因を区別する一握りの者であれば、欲界に囚われた現世における結果主義的な発想に囚われず、恵まれていようが、恵まれていなかろうが、あくまでも善因となる業に努めようとするだろう。
ちなみに、因と縁を区別しない物事を「原因→結果の連鎖」と考える外道的な欲界に囚われた思考だと、玉突きのようになって、宇宙の初期状態によって全ては宿命的に定められるという、マッカリ・ゴーサーラ(彼はタロット占いのルーツである可能性がある)の糸玉論となる。このような外道にとっては、思考も、脳内の神経回路の電子的な振舞いでしかないので、自由意志(因の側面)というものはないと考える(全て縁の側面で考える思考)。
世にはばかる、現世利益志向のスピリチュアリストの考えることなども、ほとんど縁ばかり、縁まみれの思考だということがわかる。「縁を引き寄せる・招き寄せる」などと、典型的に外道的・欲界まみれのキーフレーズだろう。
「縁」に関して良い使い方の方を言うならば、「仏縁」や「縁覚」あたりではないか。


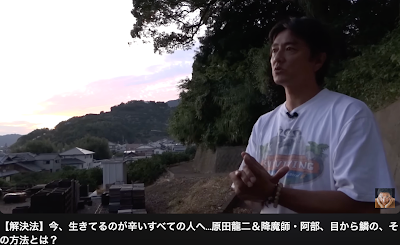
コメント