七四六家のヒロシは、ヴァンパイアと化すのか?
神智学のブラヴァツキー註 1によると、幽霊が生きた人間の側からコミュニケーションを取られ続けると、次第にそのことに味をしめるようになり、やがて幽霊の側から生者の生気を自ら求めて地上世界(人間界)から去らずに彷徨い続けるようになるのだという。ブラヴァツキーは、降霊術・霊媒師の類を強く批判する文脈でそのことを述べているが、この話は、幽鬼=吸血鬼(ヴァンパイア)のことを考える上で興味深い。
先日、心霊系 YouTuber の七四六家で、幽霊メンバーであるヒロシが、他の一部の幽霊に「臭い」と言われて露骨に嫌われる場合がある、という件があり、その「臭い」ということは、どういうことを指すのか? ということについて検証する動画が公開された。
僕はこの動画を観るなり、前述のようにブラヴァツキーが、「幽霊が霊媒によって人間の生気を吸うとやがてヴァンパイアになる」と言っていた件をすぐに想起してしまったのである。動画では「血生臭い」などという発言まで飛び出している。ナナシロたちは一応、「ヒロシが生前魚釣りが好きだった」ということで今回はひとまず話を収拾しようとしているが、もちろん彼らに神智学的なヴァンパイアに関する知識など求めようもない。
それで改めて「ブラヴァツキーの言っていたヴァンパイア」とは何だっけかな? と思って改めてまとめ直すことにした。以前にも、「神智学系の死後観・輪廻転生観を添削する」という形で神智学について駄目出ししたことがあったが、ヴァンパイアについて、原典の該当箇所など、詳細は自分でも忘れてしまっていたので、改めて該当部分の引用も含めてまとめ直そうと思う。
ブラヴァツキー(田中恵美子・訳)『神智学の鍵』(1987-02-15)p297
- カーマ・ルーパ(Kāma-rūpa, 梵)註 2
- 形而上学的に言えば、また我々の秘教哲学の観点からすると、物質に関するあらゆる精神的、肉体的欲望と思いによってつくられた主観的な形体をいう。この形体は肉体の死後生き残る。死後、7 つの本質(又は人間の本能と観念作用が順次に働く、感覚と意識の 7 つの世界と言おう)のうちの低級 3 本質、即ち肉体とそのアストラル原型と生命力は、使用済となって地上に残る。それから 3 つの高級本質は 1 つの組になってデヴァチャンの状態に入るが、高級自我は新たな化身の時が来るまでデヴァチャン状態にいる。死んだ前の人格の影は、その新しい住み家であるカーマ・ローカに取り残される。 かつて人間であった時のかすかな写しであるこの影は、暫くの間生きのびるが、その期間は影に残る物質性の要素によって異なり、それは故人の生き方が決定するのである。高級マナス、霊及び肉体感覚器官を奪われているので、この感覚のない殻のままで放置されていれば、それは次第にしぼんで崩壊してしまう。だが、後に残された友人たちの熱烈な願望や哀訴により、あるいは霊媒行為の中で最も有害なものの 1 つである降霊術により、無理やり地上に引き戻されると、この“お化け”はその体の本来の寿命をずっと上まわる期間生きのびることになるかもしれない。カーマ・ルーパが 1 度生きている人間の体に帰る方法を覚えると、それは吸血鬼となり、それと一緒にいたいとしきりに望む人たちの生気を奪って生きることになる。インドではこの影をピシャーチャと呼んで非常に恐れる。
七四六家のくまこ(霊媒)を始めとする生者メンバーと、死者メンバーであるヒロシの関係がこれに該当するのではないか。
最近、くまこが「腰を痛めてリハビリ中」ということだが、ヒロシに生気を吸われている(その分、ヒロシが生気=血で生臭くなってきている)影響とは考えられないだろうか? もちろん、本人たちの間では、意図していない形であるとはいえ、メカニズムとしては、である。
素人集団である七四六家では当然ではあるものの、そもそも世間の心霊 YouTuber 業界で普通に思われていることなのだが、霊感があることを単に「視える」だけの知覚能力の問題と決め付けているフシがある。なので、取り憑かれたりしない限り、一方的に視えている分には、直接的な害はないものだと安直に思い込んでいる。
しかし、ブラヴァツキーの考える霊媒のメカニズムによると、幽霊とコミュニケーションを取る行為自体が、「霊媒者の生気を使って行われる霊媒者の脳内現象」だということだ。
問 貴下はカーマ・ローカと言われますが、それは何ですか?
答 人間が死ぬと、その低級 3 本質、即ち肉体、生命、生命の媒体である生きた人間の複体(アストラル体)は永久にその人から離れます。それから 4 本質つまり真中の本質である動物魂即ちカーマ・ルーパと、カーマ・ルーパが低級マナスから同化したものと、それに高級 3 体がカーマ・ローカにはいります。カーマ・ローカはアストラル界で、スコラ神学のリンバス、昔の人の言う黄泉の国ですが、厳密に言えば場所と言えるかどうか解りません。それは一定の領域も境界もなく、主観的空間の中にあります。つまり、私達の五感を超えたものです。それでも存在しており、動物を含み、 生きていたすべてのもののアストラル幽霊が第 2 の死を待っているのは此処です。動物達の場合には、最後にアストラル分子が崩壊し、全く消失します。人間の幽霊の場合には、アートマー・ブッディ・マナスの 3 つ組がデヴァチャン状態にはいることにより、低級諸本質即ち前の人格の低級反映から、いわば、分離する時に第 2 の死がはじまります。
問 そのあと何が起こるのですか?
答 それから、カーマ・ルーパの幽霊は情報を与える思考原則(高級マナス)をなくしてしまい、マナスの低級面即ち動物知性は高級マナスから光を受けることなく、また媒体としての肉体の脳ももうなくなり、崩壊してしまっています。
問 どんな風に崩壊するのですか?
答 低級マナスは、脳の或る部分が生体解剖者に摘出された蛙のような状態になり、もう、最も低級な動物的次元でさえも考えることはできません。そうなると低級マナスでもなくなります。低級マナスは高級マナスがなければ、何にもならないからです。
問 降霊術の会に霊媒を通して出て来る実体のないものはこれですか?
答 そうです。しかし、推理力や熟慮する力の点では本当に実体のないものですが、たとえどんなにアストラル的、流動的であっても、やはり 1 つの実体です。アストラル幽霊が磁力的、無意識的に霊媒に引きつけられて、いわば、霊媒を代理としてしばらく生き返り、霊媒の中で生きている場合はそうです。この幽霊即ちカーマ・ルーパはくらげにたとえることができます。くらげはその本領内即ち水(霊媒の特異性のあるオーラ)の中にいる間は、稀薄なゼラチン状をしていますが、水から出して手の平や砂の上に置いたり、特に日光にさらすと、忽ち解けてしまいます。霊媒のオーラの中に、幽霊は 1 種の代理的生命を持っており、霊媒の脳や居合わせる他の人達の脳を通して推理したり、話したりします。
ブラヴァツキー(田中恵美子・訳)『神智学の鍵』(1987-02-15)p139-140
つまり、ブラヴァツキーによると、幽霊(カーマ・ルーパ)というものは死者が幽界(カーマ・ローカ=アストラル界)に残した影(残像・痕跡)のようなものであり、(人ひとり丸ごとのまとまりがあるとはいえ)残存思念の延長にあるものだということになる。死者の魂はデーヴァチャンと呼ばれる天国のようなところに行って次の転生までの間、天界の幸福を享受するという。つまり幽霊は死者本人ではなく、そのアストラル体的抜け殻だということだ註 3。その抜け殻を拾って(霊媒者の脳内に入れ)、死者本人だと思って生気(霊媒者のオーラ)を吹き込んで、降霊遊びをすると、仮想の人格として一人歩きし、やがて暴走する。それがヴァンパイアだということになる。
ホラー映画『死霊のしたたり』(1985 年、ブライアン・ユズナ製作)のシリーズや『バタリアン 3』(1993 年、ブライアン・ユズナ監督)では、死者を蘇生できる化学薬品が鍵となって物語が展開するが、お約束として、蘇生した死者は正気を失っており、血に飢えた食人鬼となって生者を襲う。あれらこそまさに、ブラヴァツキー(神智学)流のヴァンパイアの実態をよく表現したドラマの好例だろう。
そう言えば、降魔師の阿部吉宏を擁するニンゲン TV では、原田龍二に預けていた座敷童みやこが、最終的に阿部さんに返還され、彼の手によって天に上げられた。阿部さんが強調していたのは「みやこがあまり長く原田家で心地良い生活を続けていると、生者の生活に執着を持つようになり、逆に悪霊化して誰かに取り憑いて意識を乗っ取ろうとするようになりかねない」という話であった。だから、頃合いを見て、天に還す必要があるんだ、と。
(みやこの話題は 13:10~23:42)
阿部さんの場合は座敷童を扱う歴史を持った一族出身のプロの霊能者であるが、七四六家では意図せずして、ヒロシに関して、原田家におけるみやこの場合と似たような経緯を辿りつつあるのではないだろうか。
註
- 神智学(ブラヴァツキー)は、正統仏教(偽仏教の大乗教ではなく現代のテーラワーダに至る系譜の南伝仏教のこと)から見ると、他の宗教思想と同じく、象を撫でている群盲(外道)の 1 人に過ぎず、要するに、彼らの妄想する思想体系は無知偏見の域を出ないもの(要するに邪見)だが、少なくとも、群盲たちのそれぞれの手で触れている部分の局所的な知見については、嘘でまかせを言おうとしているわけでもなく(そのせいで間違った自己正当感を持っていて余計に手に負えない場合もあるが)、象(真実)の一端ではある。これが、正統なパーリ経典の長部第 1 経の梵網経(cf.「梵網経の 62 邪見」)で言われていることである。
- ここで「吸血鬼」と訳されている部分の原語は「vampire」のはずだが、それを確認したいと思って原書をあたると、訳書の巻末の用語解説の部分がそもそも存在しない。いったいこれは、ブラヴァツキーの言っていることなのか、翻訳にあたった神智学協会ニッポンロッジの編者・訳者が付け加えたものなのかが不明であった。それで苦労して調べ回ってみたところ、ブラヴァツキー著の“The Theosophical Grossary”(1892)(『神智学用語集』)からの引用だということが判明。確かに原語は「vampire」であった。
- もちろんここは外道の邪見であって、正統な仏教からすれば「無我」であるので、「どの形体が本人(本物)か?」などといった真贋論は「どこかに本物の自分(真我)がある」という邪見をベースにした典型的な外道の思考様式、ということに他ならない(北米大陸を乗っ盗ったアングロサクソン系白人の子孫が「俺たちの先祖伝来の領土を侵すな!」と移民排斥をするのに似ているとも言えるだろうか? 日本の場合は大和人がアイヌから奪った土地とアジア系移民排斥の関係性に該当)。幽霊の状態であろうが、天界の天人・天女の状態であろうが、いずれも片腹痛い、というのが仏教の無我的な思考である。





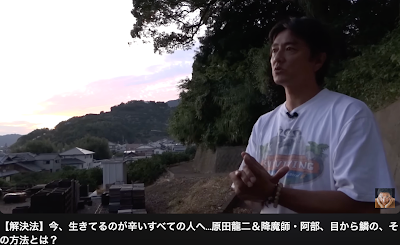
コメント