Dr. マシリト(週刊少年ジャンプの鳥嶋・元編集長)の自伝本
発刊後半年弱にしてようやく図書館での予約順が巡ってきた Dr. マシリト(週刊少年ジャンプの鳥嶋・元編集長)の自伝本『ボツ』(別の編集者による彼へのインタビューが元になっているが、著者は鳥嶋氏名義となっているので他伝ではなく彼公認の自伝と言える)を読んだ。
要するに、鳥嶋さんが週刊少年ジャンプにおいて行ってきたことは、週刊少年ジャンプを「小中学生(男子)の子供向け」として定義づけ、そのターゲットである子供読者のニーズを汲むことを徹底したことだろう。そのニーズを汲んだ方向性に漫画家を走らせること。漫画家本人の好みと合う合わないではなく、そこはビジネスとして、である。講談社の週刊少年マガジンではなく、小学館の月刊コロコロコミックの方を向くべし、である。そんな鳥嶋さんに言わせると、今のジャンプの『ONE PIECE』は群像劇だったりと、彼の考える子供向けジャンプ漫画としては邪道だという。本物の小中学生である子供向けのわかり易さではなく、精神的に大人になれないアダルトチルドレンのためのチャイルドプレイ的な読者向けだという話。だから、『ドラゴンボール』のような国境を超えて国外でもヒットするような作品になることができないのだ、と。
まあ、良くも悪くも鳥嶋さんの今のジャンプに関する評はその通りでもあるのだが、少子高齢化でターゲット読者となるべき本物の小中学生人口が減っている状況では、「子供のフリをした汚れた心を持つ大人たち」的な読者をターゲットとしたのがビジネス的には正解で、ポスト鳥嶋時代のジャンプの編集方針としてはそれはそれで間違ってはいなかったことにもなる。
その「小中学生の子供向け」というのは結局「キャラクター > ストーリー」だったり「非群像劇」ということになるようだ。要するに MCU(ディズニー映画のマーベル・スーパーヒーローもの系)と同じノリの精神的に幼稚な視聴者向けの作品群と同じテイストのもの(キャラクターが入り混って暴れ回ることが主で、ストーリー性は取って付けたもの)である。ビジネス手法としてはディズニー映画よりもジャンプ漫画の方がずっと時代的に先行していたことになる。
人気 1 位の『北斗の拳』を徹底的に研究
──たしかにキャラクターが強くなって魅力的になれば、読者はそのキャラの動向が気になるというわけですね。しかし、順位が十何位あたりまで下がると編集者としてはかなり焦りますよね。
鳥嶋 焦るけど、理由があって下がるわけだからね。理由を突き止めて改善策を見つければいいわけ。だめならそこで連載終了だよ。そうならないように、分析と対策をするのが編集者の仕事だから。
──なるほど。理由があって十何位。逆に当時の人気 1 位は『北斗の拳』ですよね。それをどう見ていたんですか?
鳥嶋 熱血漫画好きな編集部の連中が「やっと待望の作品が出てきた」って、盛り上がっているのをすごくしらけながら見ていた。副編も編集長も『北斗の拳』が大好きで、連載ネームが回ったときから、『ジャンブ』の救世主のように言われていてさ。ちょうど世紀末救世主の話だったしね(笑)。
──うまい!(笑)。鳥嶋さんは、『北斗の拳』をどう評価していますか?
鳥嶋 部内にそういう雰囲気があったから、斜めから見ていた。だけど『ドラゴンボール』が中だるみというか、人気が落ち始めて立て直さなきゃいけなくなったときに、『北斗の拳』がなぜ 1 位を取っているのか初めて研究したの。
編集部で読むのは癪だから、3 巻まで会社から持って帰った。そしたら、「ああ、たしかによくできてるな」って思ったね。1 位の漫画には、読者が好きな要素が詰め込まれているわけ。だから、その作品によって読者の嗜好を分析することができるの。
──わざわざ社外で読むんですね(笑)。職場で読むと「あいつもちゃんとやっているな」と思われてしまうから(笑)。
鳥嶋 家に持ち帰ってね(笑)。読んでみると、特に 1 話目がよくできていると思った。作画の原哲夫さんの絵の弱点をうまく補って、いいところを引き出している。原さんは一枚絵を描くのがうまいけど、劇画調だから連続アクションは得意ではない。止め絵の連続を使いながら「秘孔を突く」という演出によって、前後のギャップで見せるしかないわけ。
だから、原さんの絵が持つよさを生かしたのが、「秘孔を突く」という形なんだよ。でも、子どもがそれをまねしてギャグになるぐらいのインパクトがあるんだよね。秘礼が入るとき、「ひでぶっ」て言いながら敵が破裂したりするじゃない。ああいう見せ方がうまいなって。
──見せ場である必殺技が、作家の絵の特性とよく合っているんですね。
鳥嶋 秘孔を突くって、それこそ鍼灸院でいうツボがあるじゃない。あれをうまくアクションに持ってきたよね。『進撃の巨人』でいえば、理科室の人体模型を巨人にしたアイデアと同じ、まさにワンアイデアだ。だけど、これで『北斗の拳』というモチーフがもう立っている。「経絡秘孔」っていうのがあることによって。
──なるほど。
鳥嶋 うまいな、着眼点がいいなって。秘孔のアイデアは、原さんや編集者が出してきたんだろうけど、ドラマのエッジを立てるという意味では、武論尊さんがチームを引っ張っていたね。ドラマの背骨、つまり世紀末の救世主をどうやって作るか。その課題をどんどんクリアしていったわけだ。
武論尊さんは結局、『ドーベルマン刑事』のときも映画『ダーティハリー』からモチーフを持ってきた。『北斗の拳』は原さんが好きなブルース・リー、衣装は映画の『マッドマックス』から。だから『北斗の拳』=ブルース・リー+『マッドマックス』+武論尊の原作。漫画ってそんなもんだよね。イメージの取り入れ方がうまい。
鳥嶋和彦『ボツ 『少年ジャンプ』伝説の編集長の“嫌われる”仕事術』(小学館集英社プロダクション、2025-05-22)p72-75
「理由があって下がるわけだからね。理由を突き止めて改善策を見つければいいわけ」という部分が、投資にも通用する普遍的な話だよな〜と思った。ある銘柄の株価が下がるのは、理由があって下がる。株価が上がるのも、理由があって上がる。自分の買った株に関して、買ってみてから下がって「良い株だと、良い会社だと思ったのに、何で上がらないんだろうか?」と悶々とするというよりも、「下がるのには理由があり、上がるのにも理由がある。ただ自分がその理由に気付いていないだけ」と思って、その「理由を突き止めて改善策を見つければいい」というのは鳥嶋さんの言う通りである。そうやって突き止めた下がる理由を持つ銘柄(群)を避け、上がる理由を持つ銘柄(群)を選んでいく。そういう努力を続ければ、トレードに勝つ確率的な蓋然性を上げていくことができるのである。
「1 位の漫画には、読者が好きな要素が詰め込まれている」というのも、「相場を先導して上がる株には、投資家が選好する要素が詰め込まれている」または「今後の資金が向かう先を予測するヒントがある」と読み替えることができる。
漫画嫌いの鳥嶋さんは、漫画作品そのものを追求することよりも、漫画を読む読者(ターゲット読者層である小学生男子)を常に意識している。株で言うならば、株(銘柄)やその会社に入れ込むの(長期投資を錦の御旗に掲げる投資家はこういう側面を前面に押し出すが)ではなく、基本的にファンダメンタルズなどには無頓着で、そうではなくその株を売り買いする他の投資家(プレイヤー)の動向を意識する、という話になる。
つまり、漫画ビジネスにおける鳥嶋さんは、圧倒的に株式投資における短期テクニカルトレーダー派の立ち位置なのだろう。実際にこの本において、鳥嶋さんは、週刊少年ジャンプでは、焼畑農業とも言うべき「新人を発掘して一人前になっていく過程を使い倒す」というビジネス手法が得意で、ベテランになったら連載陣としては卒業してもらうのが普通という趣旨のことを言っているから、株の短期売買手法そのものである(まあもちろん、個別の漫画作品(個別株に相当)については短期売買、漫画家(株に紐づく会社に相当)については長期投資のようだ、と言った方が、正確かもしれないが)。
その他
- まず最初に「小学館集英社プロダクション」という名称にギョッとして、「ペーパーメディアも衰退して、ついに競合関係にあったサンデーとジャンプが提携する世の中になったんか?」と思って調べてみたら、何ていうか、元々、「一ツ橋グループ」という同族企業グループ内のお仲間同士だったということを今になって初めて知ったというオチ。ちなみに、鳥嶋さんが後に編集長となった白泉社もやはり一ツ橋グループ。
- 初期の『ドラゴンボール』の人気低迷を打開する策として『北斗の拳』を研究した結果、天下一武闘会などの「バトルもの」へと方向転換し、狙いどおり大成功した。『ドラゴンボール』で確立したこの〝天下一武闘会〟システムを『幽々白書』などの他の担当作品にも次々に適用してヒットを連発させた──という主張になっているが、どう考えてもあの武闘会システムには、ゆでたまごの『キン肉マン』の超人オリンピックという決定的な先行者があったわけで、鳥嶋さんは『キン肉マン』の存在・功績にはまったく触れないで、あたかも『ドラゴンボール』の天下一武闘会の功績であるかのように語っているのは、どうなんだろう。この人も、真っ赤な嘘は言わないにせよ、結構、情報・心象操作する人なんだなと、ちょっと残念に思った。
- 鳥嶋さんという人は、本を読む限り、徹底したビジネスライクな個人主義、スタンドプレイヤーに思われ、そこは悪いというよりは良い形で功績を上げてきて、悪い意味での組織主義とその弊害に対して戦ってきた人という印象だ。特に、子門真人の『およげ! たいやきくん』の印税問題など、昔からフジテレビはアーティスト・クリエイター側には利益を回さずに美味しい部分は自分らで独占していたわけだが、そこをフジテレビ・東映アニメーションに対して漫画家の利益を確保する闘いを繰り広げた部分には圧倒的に肯定的な印象を持った。
- だが、一方で、上記のように、週刊少年ジャンプにおけるゆでたまごの『キン肉マン』の功績については全く無視して黙殺するなど、ここでは個人主義、スタンドプレイヤーとしての悪い面も出ていると思う。当時、ゆでたまご陣営と鳥山明陣営では激しいライバル意識による確執があったようで、ゆでたまご嶋田も X でそのような発言をしているが、鳥嶋さんという人は、基本的に自分が編集で担当した人とか何らかの縁がない人は良くも悪くも徹底的に無視するタイプの人なのかもしれない(ちなみに『北斗の拳』の武論尊については彼が担当していたことがある関係)。組織内の政治には基本、無関心とも言っているし。
- とはいえ、元編集長という立場の人なのだから、鳥嶋さんの自伝を読んだ世間の一般人が、彼の発言を元に、週刊少年ジャンプの歴史を歪んで受け止めかねないミスリードする発言はどうかとも思うわけである。後に彼が次々にヒットを出した担当作品で使い回した天下一武闘会システムは『キン肉マン』からパクったという点は、揺ぎない事実だろうから。




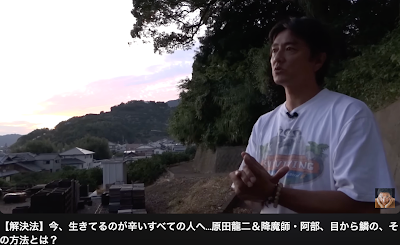
見知らぬ物が、突然のコメントをすみませんm(_ _)m
返信削除ししおどしさんの過去ブログの記事でご質問があるのですが、よろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
コメントする場合は、該当する記事にお願いします。また、コメント不可能な記事については、コメントを受け付けておりません。
削除