ダンジョンズ&ドラゴンズの 2 次元的キャラクター属性
最近、実写化映画の第 4 作目(リブートとしては第 1 作目)が公開された『ダンジョンズ&ドラゴンズ』だが、マーベル・シネマティック・ユニバースや DC・エクステンディット・ユニバースのチープなクローンのような作りになってしまって残念だった。旧 3 部作が、直接・間接に 1 作目の監督・製作者である Courtney Solomons(2 作目は製作総指揮、3 作目は所有する After Dark Films を通じた配給権)の影響下にあって、作を進めるごとに確実にマイナー化していくのに反比例して、Dungeons and Dragons (aka. DnD) の実写映像化としてはグングン良くなっていった。つまり、ショービジネスとして敗北の道を辿りつつ、DnD というゲーム素材の実写化作品としては、どんどん良くなっていたのだが、製作する側としてはそんなつもりはなく、もっと儲けられる素材として捉えていたようで、著作権者である Wizards of the Coast の親会社の Hasbro が業を煮やしたのか、「儲かる」ポップな方向性でリブートさせた最新作だったのだろう。Box-office bomb とまではならなかったものの、期待されたほどの大した黒字ではなかったようだ。
最新作は、案の定、お安い「家族愛」を盛り込み、各年齢層用にキャラクターを一通り揃えた作りで、マクドナルドのハッピーセットのように企画されたものだった。しかし、DnD のファン層が、マクドナルドのハッピーセットに歓ぶ層ではない、例えば次郎系ラーメンを目指すようなオタク筋であったのが第 1 の敗因。しかしこれはおそらく製作者側もわかっていたことで、DnD のファン層向けに作っていたら、ショービズ的な儲けができないことは、旧 3 部作が示していたから、今回は敢えて、ショービズ的なファミリー層を狙って行くつもりだったのだろう。第 2 の敗因は、各年齢層用にキャラクターを一通り揃えたせいで、肝心の主人公の存在感が一番薄くなってしまったという点である。クリス・パイン演じるあの主人公の吟遊詩人は、単なるお安い「家族愛」要員としてしか、存在する意味がなかった。あいつは絶対に要らない。ミシェル・ロドリゲス演じる女バーヴァリアンの方がずっと少女に対する愛情がキャラクターとして演出されていた。役者の演技の問題ではない。企画・脚本の段階で、あのクリス・パインが演じていた主人公は存在自体が要らなかったのだ。少女の実の父は、ヒュー・グラントの演じるペテン師ということにして、ミシェル・ロドリゲス演じる女バーヴァリアンが主人公を演じて、悪い実父から少女の愛を勝ち取る養母とするべきだった。
あと、時代的に、今さら大作映画路線で DnD という素材をリバイブしようとするのではなくて、Netflix とかのドラマシリーズとして描くのであれば、キャラクターをあれこれ盛り込んでも、どうにかなったのではないかと思う。20 年前に Courtney Solomons が映画化権を購入した段階ではまだどうしようもなかったが、DnD はどう考えても、素材的にドラマ向きである。
最新作の失敗と対照的に、旧 3 部作は、マニア向けにどんどん良作化していたと、つくづく思う。1 作目にしても、5 〜 10 回のドラマシリーズにして、女王サヴィーナと魔術師プロフィオンの政治的対立というマクロな場面と、主人公である盗賊リドリーたち一行のサヴリールの杖を巡るクエストとの場面をカットバックして丁寧に描ければ、もっと楽しめたと思う。
2 作目は、正義(善)の騎士・僧侶・女エルフの魔術師・女バーバリアン・小男の盗賊という、パーティー構成からして、無茶苦茶いかにも正義のクエスト部隊という、垂涎のメンツである。
そして 3 作目。これがもう、ヤヴァい。前作の反動なのか、今回は、悪者が(ほぼ)主役。1、2 作目でやられ役だったダモダーみたいなダークな出で立ちのキャラクターたちのパーティーを巡る話。暗殺者のヴィマックとかヴァーミン・ロードのベズの存在感がかなりヤヴァい。親玉のシャスラックスとか、もうほとんどクトゥルー系ホラーの域。最後に主人公が闇落ちするストーリーだったら、もっと良かったが、さすがにそれは(本来、ホラー映画ではないので)企画的に無理だったか。
2 作目で善、3 作目で悪を描いたのが対照的で面白かった。両作とも、Courtney Solomons の影響下、Gerry Lively 監督作品である。
DnD の 2 次元的キャラクター属性
僕自身は、DnD のプレイ経験は基本的にゼロであるが、NetHack をやった経験から、DnD 的なルールには部分的に親しみがある。
キャラクターの属性で特徴的なのが、一般的な善 ↔ 悪という対立軸だけではなく、秩序 ↔ 混沌というもう一つの対立軸があり、この両者による 2 次元的なものとなっている点だ。(ちなみに、いずれの軸においても、中間的な状態を示す場合は中庸と表現される。)
| 混沌 | 中庸 | 秩序 | |
|---|---|---|---|
| 善 | 混沌・善 | 中庸・善 | 秩序・善 |
| 中庸 | 混沌・中庸 | 中庸 | 秩序・中庸 |
| 悪 | 混沌・悪 | 中庸・悪 | 秩序・悪 |
興味深いのは、「秩序 ↔ 混沌」の軸の方である。これ自体に善・悪の意味はないというのがポイントである。
秩序は、何らかの信念・倫理観を重視する状態を示し、それに対して混沌というのは、人生は運や偶然に支配されているといういわば即物主義・結果主義的なものを示す。
現実世界の物事に対応させてみると、要するに、秩序は霊性主義のことであり、混沌の方は自然科学を含む物質主義のことである。自然科学(量子力学を除く)というのは、偶然の確率の積み重ねによってこの宇宙が成立しており、そこに何らかの人為的意思の介在というものを認めない体系だからである。
そして、簡単にわかるように、スピリチュアリストにも黒魔術使いのような悪人はいるだろうし、物質主義者にも善人はいるだろう。つまり、善悪と「秩序 ↔ 混沌」の軸は独立した要素なのである。
仏教の欲界との対応
DnD の 2 次元的属性の考え方を僕の仮説「善趣と悪趣」に基いて修正すると、次のようになる:
| 混沌 | 中庸 | 秩序 | |
|---|---|---|---|
| 善 | 地居天 | マノーパドーシカ | キッダーパドーシカ |
| 中庸 | 人間 | ||
| 悪 | 餓鬼 | 畜生 | 地獄 |






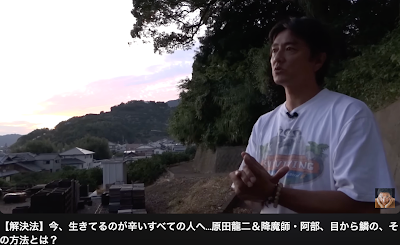
コメント
コメントを投稿